| 滋賀の生協 No.166(2014.3.31) |
 |
滋賀県協同組合講演会 次世代につなぐ協同組合 ~七代目が語る二宮金次郎が遺したもの~ 2014年3月1日(土)14:00~16:00 滋賀県農業教育情報センター研修室 主催 国際協同組合年(IYC)記念滋賀県協同組合協議会 講師 中桐 万里子さん (親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」代表、京都大学博士) |

| ◆プロフィール 中桐 万里子(なかぎり まりこ) 一九七四年生まれ。二宮金次郎(尊徳)の七代目の子孫。慶應義塾大学環境情報学部卒。京都大学大学院臨床教育学専攻。博士号取得。関西学院大学講師。二〇〇七年より親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」主宰。著書に『二宮金次郎の幸福論』(致知出版社)などがある。 |
| 実践家二宮金次郎 |
 みなさま、こんにちは。中桐と申します。 みなさま、こんにちは。中桐と申します。私の先祖の一人でもあります、二宮金次郎をめぐってお話をする中で、一体金次郎は、協同組合、あるいは協同をどんな風に考えていたのか、そんなお話ができたらと思っております。 私は金次郎から七代目に当たる子孫ですが、家の中では、祖母、そして母から繰り返し金次郎の話を聞いて育ちました。今日お話しする内容もまた、家族たちから受け継いできたことの受け売りということになります。 金次郎と言えば、五六歳の時にその名を尊徳(たかのり)と変え、これが通称尊徳(そんとく)と呼ばれる所以になるわけですが、この響きよりも、小学校の校庭の薪を背負って本を読んでいる少年の像のインパクトが強い人物ではないかと思います。金次郎のこの像、みなさまはどのように思っておられるでしょうか。多くは「勤勉な少年」「勉強を良くした」「本をよく読んだ」、そんなイメージでとらえられるのです。 |
| 一歩ふみ出す足 |
| ところが、私は家族から全く違うことを聞いてきました。「これは勤勉の象徴ではない」と言うのです。手に持っている本が重要なのではなく、大切なのは背負っている薪であり、もっと大切なのは一歩を踏み出している足であります。もちろん本を読むことや、勉強することも大事だろう。でも、どんな時でも働く事、行動すること、くじけず、あきらめず一歩前に足を踏み出すことをやめてはいけない。それが金次郎の願いなのだと言うのです。 なぜ家族がそんなことを言うのかというのは、どうやら成人の後の金次郎の発言に理由があったようです。金次郎は、身長一八二センチ、体重九四キロという大男だったと記録されています。縦にも横にもとても大きかったこの人物は、七〇歳までの人生を送りました。 七〇年の人生を閉じる時に、金次郎は「私の名を残さず、行いを残せ」という遺言を残しました。墓も立てないでくれと頼みます。但し自分には残してほしいものがある。それがあなたの行動、あなたの一歩、あなたの実践なのだと言うのです。あなたの実践をたゆまず続けること、行いを残すこと、そのことで未来を切り拓いてほしいというのが願いでした。 金次郎は最期に「行い」という言葉を残すほど、人生において徹底して実践にこだわりました。但し「実践」、そんなにたやすいことではないことも知っていた。だからこそ、波乱万丈だった金次郎の七〇年の人生に、きっと何かがあるはずだ。それを手掛かりにあなたたちの行動を残してほしい。行動主義、現場主義、実践主義、それこそが金次郎の人生だったわけです。 |
| 天保の大飢饉 |
| では「実践」とは何だったのか。それは農業ということでした。しかし、農業、単純ではない時代。この時代は異常気象が続いたからです。自分たちの思う通りにはならない自然達と、どうすれば共存共栄し、農業を実らせることができるのか。そんなことが大きな課題だった時代です。 災害に苦しむ時代に、もはや本に書いてあるきれいごとは何の意味もないのではないだろうか。私たちを本当に幸せにしてくれるのは、現実的な幸せ、目の前の田んぼや畑が実ってくれることだと、金次郎は思うようになりました。道徳や精神論ではなく、むしろ経済、現実的で具体的な幸福ということが金次郎の一番のこだわりだったわけです。 そしてこのことにこだわり、生涯に六百以上の被災地の村々の立て直しに関わり、経済を復活させ、そして希望を復活させます。この不遇な時代、金次郎は一体どうやって、六百もの村を再建できたのか。一番有名な事例を紹介します。 それは田植えが終わった季節だったと記録されています。大変な重労働の田植がようやく終わってホッとしている時期に、金次郎が村を駆け巡って「たった今植えた苗を全部抜いて捨てて欲しい」と言います。「気でもおかしくなったのではないだろうか」と多くの人は思いました。 でも金次郎には理由があったのです。「さっき食べた茄子の漬物が秋茄子の味がする」。つまり、これから本格的な夏が来るという季節に、茄子の味はすでに秋であり、これから冬が来ると伝えている。「今季は冷夏がやってくる」と判断したのです。当時の米は、冷夏が来たらひとたまりもない、寒さに弱い作物だったのです。金次郎は「ともかく米はあきらめよう」と言う。でもあきらめるばかりでは死へと向かいます。だから「植え替えをしよう」と提案したのです。稗とか粟、蕎麦や大根のような、冷夏時でも育つ寒さに強い作物に植え替えてくれと言いました。 「でもこれは博打だ」と人びとは感じます。天候は神様だけしか知らないことなのに、なんで金次郎がそんなことをわかるというのだろう。さらに言えば、米の値段と雑穀の値段なんて比較にならない。そんな植え替えをしたら破滅に導かれるではないか。そんな博打のためになんでそんな苦労をしなければならないのかというのが本音でありました。でも、金次郎の提案は最終的に受け入れられることになりました。 するとこの年から飢饉に襲われます。後に「天保の大飢饉」と呼ばれる歴史的な災害でした。数年に及んで日本には夏が来ません。年間百万人以上の人間が餓死へと向かったと記録されています。どの村もが死体の山で埋め尽くされる、地獄のような時代になって行きます。 しかし、金次郎の村は奇跡の村となります。餓死者が一人も出なかった。蕎麦も大根も稗も粟も、その寒さの中実ることに成功してくれたのです。 金次郎は「どんな境遇とも私たちは共存することができる」「どんな環境の中でも必ず幸せを手にできる」そのことを実証し、伝えようとした。そんな人生を送りました。 こんな話をすると「金次郎の神業にしか過ぎないのではないだろうか」と思うかもしれません。しかし、これは金次郎一人の神業ではなかったのです。彼は、六百の村に住む一人ひとりが実践できるように、行動の秘訣を語って行ったのです。 |
| 水車と川の関係 |
|
じゃあ、どう行動すればいいのか。金次郎はそのことを語る時、毎日農作業に使っていた道具をヒントに語りました。「わたしたちは水車みたいに動けばいい」という言葉でした。 「水車と川の関係」。これが理想的な共存共栄の関係だというのです。 水車と川は全然違う形をし、全く違う方向性で動いています。形も、硬さも、成分も違うし、個性も違う、働きも違う、動き方も違う。全く違うものどうしが、見事にお互いを活かしている。そしてエネルギーを生み出している。水車にも川にも全然無理がない。「こんな理想的な関係はないのではないだろうか」と言うのです。 そして、「自分を水車、相手を川だと思ってほしい」と言うのです。相手はなんでもかまいません。例えば、仲間や、家族や、子どもたちでも良い。上司や部下や地域の人、そういう他者ということでもかまいません。農業をするときには自然、今自分が抱えている課題ということも相手です。自分が向き合っている現実を「川」だと思ってほしいと言うわけです。 私たち水車が無理なく回り、エネルギーという実りまで生み出すにはどうしたら良いのか。 金次郎は言います。「私たちが回ろうとしたとき、最初にすることは何か」まず思い切って目の前の川に飛び込んでいくということ。現実に思い切って飛び込むことが全てのスタートです。但し、飛び込んだままだと沈むか、流されてこわれます。だからもう一つ重要なことは、飛び込んだ場所に思い切って踏みとどまり、川から這い出してくるということです。実は水車の上半分は、川とは逆向きに動いています。思い切って飛び込まなければ回らないけど、必ず這い出してくる必要があります。そして上半分は川とは違う動き方をしなければいけないのだと言うのです。(図) |
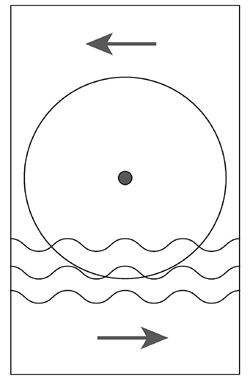 (図)水車と川の関係 |
| 従い、逆らう |
|
金次郎はこのことをこんな言葉で表します。「相手に半分従い、半分逆らう」これこそがベストな絆の持ち方であり、お互いが幸せになる。そんな方法なのだと言うのです。 では、最初にしなければならない「従う」って何だろう。「飛び込む」って何なのだろうか。それは「相手の言いなりになりなさい」ということではありません。それでは流されてこわれていくことと一緒です。「従う」それは相手を「知る」ということ。そして現実を直視し、覚悟を決めてその現状を受け入れることからスタートしてほしいと言うのです。 なぜこんなことをしなければいけないのか。私たちが川から這い出ていくため、つまり「逆らう」ためです。じゃあ「相手に逆らう」とは何か。それは、戦う、競争する、敵対するということではない。「逆らう」それは相手を受け入れる覚悟をした上で「対策」を練っていく、さらに、技術や知恵を絞って「工夫」をするということです。だからこそどんな時代もどんな環境も実りにむけることができるのではないかと言います。 但し、どんな対策も工夫も、頭の中、心の中にあるだけでは何の意味もない。声に出すこと、行動に移すこと、現実に形にすることが重要だというのです。 金次郎は「秋茄子の味」を知ります。そして、農民にとっては決して受け入れたくない「冷夏が来る」という現実を直視し、それを受け入れる覚悟を決めたのです。だからこそ、思い切った「植え替え」という対策を仲間たちに告げます。そして仲間たちとともに植え替えという行動へと向かっていった。それが餓死ではなく、実りに向かうための大切な方法だったということです。 農民たちは「こんな夏の寒さなんてやってこなければ幸せに暮らせたのに」「こんな時代にさえ生まれなければ豊かにくらせたのに」「自分たちにもっと力や権限があれば幸せにくらせるのに」と現実を批判したり、嘆いたりしました。金次郎はそんなとき「あなたたちの嘆き、それはちょうど川に飛び込むことを忘れた水車みたいなものだ。現実に向き合うことも、飛び込むこともしないで、きれいごとや妄想に逃げ込もうとしている。それがどんなに正しいことだったとしても、そこからは何も 生まれないのだ」と言いました。 幸せ、実り、それは現実の中にしか生まれない。だからこそ、どんな現実だったとしても飛び込むことからスタートしようというのが、金次郎だったのです。 但し、「どんな現実も必ず実りを生む力を持っている」と彼は考えていました。一見すれば、夏の寒さは敵にしか見えない。でも夏の寒さだから蕎麦や稗や粟を育ててくれると言うのです。 「実は相手を敵にしてしまうのは、自分自身なのだ」と彼は繰り返します。自分にこだわるから敵に見えてくる。「私は米が食べたい」とこだわるから、夏の寒さが敵に見えるだけである。「ここは米のための田んぼだ」とこだわるから、植え替えという対策が厄介な出来事のように感じる。自分にこだわるほど、世界は敵に満ちていくのではないか。思い切ってこだわりを手放して現実に向き合った時、私たちには道が見えてくると言うのです。 一見敵に見える相手をどうすれば味方にすることができるか。一見害でしかない出来事をどうすれば仲間として活かすことができるか。敵に見える夏の寒さとも金次郎は協同しようとした。win-winのお互いに幸せに向かう。そんな知恵を凝らそうとしたということです。 |